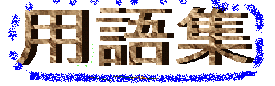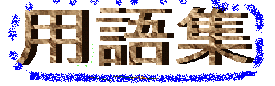用語集
海上自衛隊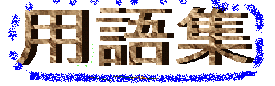
あちこちに出てくるいろんな専門用語がわからないという人のため、
ここに用語集を作りました。項目は逐次追加していく予定です。
注意! ここにある用語の意味は一般的でないものもあります。
あくまでも個人の責任において使用してください。
| あ行 |
か行 |
さ行 |
た行 |
な行 |
は行 |
ま行 |
や行 |
ら行 |
わをん? |
|
あ行
- 愛
- 親子、兄弟などが互いにかわいがり、いつくしみあう心。いとおしみ とあります。わが隊においては教官の学生に対する心でしょうか。親の心子知らず。学生にはわからないかも・・
- アイエムシー(英:IMC)
- Instrment Metorological Conditionの事。計器気象状態と訳される。ひとことで言えば天気がよくないという事か。
航空機を運航するに当たって気象状態は非常に重要です。気象状態を大きく分類してVMCとIMCと呼びます。VFR(Visual Flight Rule)
で飛行できるか、IFR(Instrument Flight Rule)でないと飛行できないのかということです。VFRはたいていの場所を自由に飛ぶ事ができますが
IFRは指定された空域を指定された方法でしか飛ぶ事ができませんが、天気が悪くても飛べるという利点があります。
したがって、民間航空の旅客機などはたいていはIFRで飛行しています。当課程においては「基本飛行」を習得するところなので、IMC下ではフライトできません。
飛行場におけるVMC、IMCの違いは、飛行場灯台を見る事で一目でわかります。学生はスケジュールによって、飛行場灯台を希望の星としてみる事もあるようですが・・(お願い、まわって・・・)
- アイシング(英:ICING)
- 気象用語で氷がつくこと。航空用語で翼などへの着氷。飛行機は高いところを飛ぶため、夏でも氷点下の環境下に置かれる事がある。空中に、
過冷却水滴が存在すると衝突した刺激で結氷が始まる。飛行機の場合、主翼や胴体等あらゆる部分に付着する可能性がある。
氷が付着すると翼型がかわり、揚力の低下、抗力の増加により燃費が悪化し最悪の場合飛行不能になる。つまり墜落。
よってたいていの飛行機はアンチアイサーやデアイサー
を装備しており、着氷を防止したり、着いた氷を取り除けるようになっている。残念ながらT−5には
エンジンアンチアイサーとピトーヒーター、デフロスターのみしか装備されていないため、アイシング状態下での飛行はできない。
- アライン(英:Align)
- 滑走路上、あるいはその延長上にきちんと乗る事。とくにベースからファイナルに旋回するときのバンクの調整が難しい。
これができないと罵声が飛ぶ事もよくあるらしい。「ちゃんとアラインせんか、どこに行ってるんだ!ああー」とか。
- アンコロ(英:ANTI COLLISION LIGHT
- アンチコリジョンライトの略称。日本語で衝突防止灯。別にこのライトがあると衝突を自動的に回避したり
衝突防止のアドバイス(T-CASS2?)してくれるわけではなく、単に他の飛行機から見えやすいというだけのもの。
KM−2では赤のローテーションライトだったが、T−5では白色のフラッシュライトになった。
法的には5700Kg以下の航空機への装備義務はないが海上自衛隊機は全機種とも装備している。
- イヤマフ
- イヤーマフラー。ちょっと見は不恰好なヘッドフォンのようなものです。エンジン起動中の航空機は騒音の塊ですから、これに近づく時には耳を保護しなければなりません。
- イーエルピー(E.L.P)
- Emergency Landing Prosedure。エンジンが停止した状態で、不時着場(訓練では滑走路)にきちんと着陸する練習。接地点の真横のポイントにおいてエンジン出力を12PSI(これがゼロスラスト)
に設定し、そこから脚やフラップを降ろして、風を読んで経路を修正して着陸する。慣れないと(慣れても?)とっても難しい。CABでは「制限地着陸」と呼んでいる様だ。
- ウエークタービュランス(英:WAKE TURBULENCE)
- 大気中に生じる不規則な流れ。その原因が航空機の翼により生ずるものをいう。後方乱気流のこと。その強度は航空機の重量と速度に関係するといわれ、
当然重い航空機ほどその強度も強くなる。航空機の総重量によりH(heavy)、M(middle)、L(light)の三つのカテゴリーに分けられ、管制基準によりそれらの管制間隔(セパレーション)
を取らなければならないようになっている。あのP−3Cでさえmiddleである。heavyは300000lbs以上の航空機。
- ウエーブ(英:WAVE)
- 本来は波、電波のこと。ここでは婦人海上自衛官を意味する。ちなみに、陸上はWAC(ワック)、航空はWAF(ワフ)
と呼ばれる。3自衛隊を比較すると海上自衛隊が一番響きが良いと思うのは私だけでしょうか。でも女子航空学生の事はあまりウエーブとは呼ばないなあ。
- ウエザー
- 天気の事。最近のテレビでもこの言葉を使うようになっていますのでご存知の方も多いでしょう。航空機にとってウエザーは非常に重要です。
したがって学生さんもこれの知識を身につけるよう厳しく指導されます。少なくとも天気図を見て、明日の天気はどんなもんかぐらいは判るようになってもらわないと・・
Dステージでは、機長の出発前の確認事項の一環として、ウエザーブリーフィングをしてもらいますが、たいていの学生は予報官の言った言葉を適当に作りなおして説明するため、
自分でも何を言っているのかわからないという状況になります。困ったもんだ。
- エプロン(英:APRON)
- 航空業界では格納庫やターミナルの前の舗装された区域のこと。すなわち駐機場。おばさんが家事を行う時に着る「割烹着」これも死語だなあ
のことではありません。でも前にあるものという意味で、語源は一緒です。(確認しました!)場所によっては
「ライン」と呼ぶこともある。ちょっとニュアンスは違うけどさしている場所は同じ。ようするに、格納庫から出した飛行機を
エンジンをかけたりタクシーを開始したるするために並べておくところ。写真はこちらでどうぞ。
その昔、学生のころは「エプロンダッシュ」と称して走った(走らされた)恐怖の場所だった。
- エリアキープ(AREA KEEP)
- 訓練空域を保つこと。うちのエリア(第8訓練空域)はただでさえ狭いのに、そこを更に13の小さなエリアに細分している。
ひとつの小エリアの大きさはざっと10マイル四方。飛行機の速さを平均120ノットとすれば、隅から隅まで飛行したとしても
5分で通り過ぎてしまう。誤差や旋回半径を考えると直線部分はせいぜい3分程度しか取る事は出来ない。諸元(高度や速度)を修正するだけで
軽く3分は経ってしまうから、要領が悪い学生は常に「エリアキープのための旋回」をしている事になり、肝心の課目が出来なくなってしまう。
- エルロン(aileron)
- 〔空〕エルロン,補助翼.のこと。飛行中は飛行機のロール方向の管制をする。車のハンドルと違い、単に飛行機の傾きだけをコントロールするので旋回中(バンクが確立した状態)では、エルロンは中立である。
これがわからないと、エルロンを取りつづけるために果てしなくロールを続け、エルロンロールになってしまうので注意!まあ、その前に機首が下がって急降下になるけど。
飛行機の種類によって、操縦輪で操作するものや操縦桿で操作するものがある。海上自衛隊の飛行機は
すべて操縦輪である。見た目が車のハンドルのように見えるせいか、タクシー中、エルロンがパタパタ動いている事が良くある。
そう、学生さんが右に曲がりたいがためにエルロンを右に取ったりしているのだ。タクシー中の方向管制はラダーで行うから、ホントはラダーがパタパタしなければならないのだ。
- エレベーター(elevator)
- 昇降機、物を持ち上げる人、もの。ではなくて、飛行機では昇降舵のこと。通常は、水平安定板の後方についている。操縦輪を前後に動かす事によってこれが上下に動き、水平安定板のキャンバがかわって、飛行機のピッチをコントロールする事ができる。
真面目な話の解説はラダーの飛行機に譲る。体験搭乗などの時、これをゆっくり引いてからゆっくり押すと、しばらくの間無重力状態となり、キャーキャー言われて楽しい。(^。^)
先頭へ戻る
か行
- 階級章
- 自衛官の階級をあらわす徽章。軍隊は階級社会であり、それを端的に表すのがこれである。上は海上幕僚長から下は3等海士まで。18段階に区分されている。詳しくは
こちらへ。
- 開隊記念日
- 小月基地の開隊記念日は例年5月に行っていたのですが、今年は秋の自衛隊記念日行事と合わせて大々的に行う事になっているそうです。したがって、年22回あった体験搭乗のチャンスも今年は一回のみとなりました。
だいたいどこの基地でも行う基地開放行事ですが、学生さんもいろいろな作業に借り出されて大変忙しい思いをする日です。でも自衛隊の外の一般の方と接することができる貴重な日でもあります。
- 外出止め
- 営内者(隊内に居住する事を義務付けられた隊員。学生も営内者です)が自衛隊の施設から外に出る事を外出と言う。で、何か悪さをしたり、悪い事じゃなくても病気になったり怪我をしたりすると、これが発動されます。
学生にとって最も恐れられている言葉のひとつ。「おまえ、1ヶ月間外出止めじゃ」「ひえー」という感じ。
- かくにん(確認):英語でチェック
- 確かに認めること。飛行作業において、確認は必須です。何事をするにもすべて確認。T−5の操縦において、まずすることは、飛行前点検。
おっとその前に、「機長の出発前の確認」をするんでしたっけね。乗りこんでからも、プリスタートチェックリスト、エンジンスタートチェックリスト、
プリタクシーチェックリスト、エンジンランナップ(つまりエンジンの確認運転)、プリテイクオフチェックリスト、アフターテイクオフチェックリスト・・・・
という用に延々とチェックすなわち確認が続く。もちろん飛行中は「高度!」「エアスピード!」と諸元が狂うとすぐチェックされる。
着陸後も・・・。そして当面の、最大の確認はソロチェック。ね、確認だらけでしょ!(@_@)
- 甲板掃除
- 簡単に言えば掃除の事。海上自衛対においては、掃除のことをすべて甲板掃除と言う。これはもちろん船の甲板掃除から来た言葉。同様に、外出の事を「上陸」と言う事もある。
- 管制圏
- 告示で指定された飛行場の周辺の空域。通常は半径5マイルの円柱状で、地表または水面からの高度は飛行場によって異なる。一般に自衛隊関係の飛行場の上限は高い事が多い。管制圏内は、管制塔との交信が義務付けられる。
- 関門ポイント
- 小月飛行場にVFRで進入する際のvisual reporting pointで関門橋の上空。つまり、ここの上空でタワーから着陸のために必要な情報をもらう。「小月タワー、ルーキー○○、オーバー関門、フルストップ。インフォメーションチャーリー」
などと言うのだけれど、聞き様によっては次のように・・・「ozuki t/w.rookie00.大バカモンfor landing..」
同じようなポイントに、サンヨー(山陽)、田部ポイントがある。「おばさんよー for landing・・・」
- 技量
- 物事を行なったり扱ったりするうでまえ。手なみ。手腕(しゅわん)。とある。飛行学生にとってこれを身につけることが、修業への道。これが、不充分で罷免になる事を「技量免」
自分の都合で学生を辞めることを「自己免」という。
- ぎざ(GIZA?)
- これは説明が難しい。飛行関係の作業(地上、空中を問わず)において、法に触れない程度の大きな失敗?をした場合に納めるもの。現金であったりモノであったりする。
これらの事柄(失敗の内容、及び納めたもの)を記録したものを「ギザ帖」と呼ぶ。たいがいの飛行隊には備えてある(はず)。もちろん当201教育航空隊にも備えられている。教官、学生を問わず利用されて?いる。
「ギザ」の語源については不明だが、昔、コイン一個を納めていて、その回りにはぎざぎざがついていることからこう呼ばれたと言う説もある。ちなみに現在のギザ一丁は500円。確かに周りにはギザギザの文字が刻まれている。
他に情報があるひとや正確な語源を知っている人がいたらメールください。
- 機長時間
- 単純に言うと、その航空機の責任者として運航に従事した時間。運輸省航空局の規定によるともっと詳しく説明されていてなかなかにややっこしい。たとえば、検定官として同乗した時間とか、
指定養成施設において、認められた時間とか、いろいろな場合が機長時間として規定されている。何でこの機長時間が大事かと言うと、ライセンスを取るための要件(つまり条件ね)として最低限満たさなければならない機長時間が定められているからなのだ。
これが結構厳しい条件で、事業用操縦士だと、飛行時間で200時間(養成施設で150時間)そのうち機長時間は100時間(養成施設は70時間)と言うように決められている。で海上自衛隊の変わっているところは、パイロットでなくても機長になれると言うこと。
つまりタコ(TACO)でも機長になれるのだ。海上自衛隊の機長は「適当と認められた者」だから、操縦士でなくても大丈夫。
- キャンセル
- 取りやめになる事、あるいは取りやめ。予定されたフライトが天候不良とかでできないときにこの言葉が流れる。学生にとって(状況によっては)うれしい言葉だろう。
でも、問題が解決されたわけではなく先送りされただけなんだよーン。規定されたフライトはきちんと終わらせないといけないのだ。
- 教証(日:きょうしょう)
- 教育証明の略。つまり、航空法において飛行のライセンスを持っていない人に対して飛行機の操縦を教えてやったもいいよと言う技術を持つと認められた人に与える免許のようなもの。
これを取るのが大変なんだ。その試験は、事業用なんかと同様、学科試験と実地試験があって、両方に合格しないともらえない。今日本で何人ぐらいいるのかなあ。教証を持っている人。ちなみに1年半前で1600人弱でした。
- 計器飛行
- 航空機の姿勢等を計器のみに頼って行う飛行方式の事。しかし計器飛行方式とはそのニュアンスが異なる。これがきちんと理解できれば、徳島の課程は卒業できるか?類似用語に「計器航法」と言うのもあり、これも微妙に異なる。
当課程で計器飛行方式での飛行を行うことはないが、基本計器飛行の訓練は行う。(Cステージと呼ぶ)この時、学生は、外界が見えないようにフードと呼ぶ目隠しを着けて計器のみで姿勢の管制をする方法を練習する。
- 検定
- 一定の基準のもとに検査をして、価値、品質、資格などを決めること。飛行教育において必須のもの。これにいろいろな名前をつけて「ソロ検定」「中間検定」
等と呼ぶ。教育の課程においては各ステージごとに、中間検定と最終検定が行われる。検定に合格しないと先に進めないのは自動車学校と同じ。ただし、飛行教育は
検定飛行以外でも、不合格が出ると言うところが厳しい。つまり毎フライトが真剣勝負なんだね。じゃあ、普通の教務フライトと検定フライトのどこが違うのかと言うと
教務フライト(普通の同乗飛行)は失敗しても教官に教えてもらえるし、やり直しが出来る、わからないときは教えてもらえると言うこと。検定飛行では、自分の技量をチェックされるわけだから
何かあってもすべて自分の判断、自分の技量で解決しなければならないと言うこと。教官は見ているだけで、乗っていないものとして考えなければならない。だから、飛行時間の処理上も「機長時間」となるわけ。
まあ、何と言っても一番印象に残るのは「ソロ検定」だろうなあ。
- 航空身体検査
- 航空機の搭乗員(一般にはパイロット)は最低、年に一度の航空身体検査を受検し、合格して有効な航空身体検査証明をもらわなければなりません。
これは自衛隊も同様ですが、受検は自衛隊内の航空衛生隊というところでします。内容は一般的な身長、体重のほかに視力関係(視力、斜視、焦点、視野等)や、聴力、歯科、循環器系と広範囲に及びます。ちょっと変わったところでは
耳管通気といって、鼻をつまんで「フン」とやって耳が「プシュ」と抜けるかどうかの検査や、呼吸停止が50秒以上できるかどうかなんかも検査します。とりあえず今年の分は合格!。良かった。(^。^)
先頭へ戻る
さ行
- しお(塩)
- 夏期、非常に暑くなってくると、T−5の機内は50度以上の高温になります。そりゃそうですよね。見てくださいよ。キャノピーが非常に大きく、コックピットは
まるで温室なのですから。当然その中に乗っている人は非常に汗をかきます。もちろん下着を着ていますがそんなもんはすぐずぶ濡れ、飛行服に染み出した汗は乾いて真っ白に塩を吹くのです。
で、その塩分を補うために、あちこちに「塩」を置いておき、水分補給と同時に塩分の補給も行います。どこかの工事現場と一緒ですよね。
- シーリング
- 雲の天井の事。上空を見上げて、全天に対する雲の量を八分の一単位で観測し、八分の五以上の時シーリングと言う。
これが1000フィート以下だとIMCになってしまう。
- しきしょ(日:指揮所)
- 飛行指揮所のこと。飛行当直教官や、その他のたくさんの教官がたむろするところ。もちろん学生も用事があれば入って来れるが、あまり入りたがらない。
ここで、当日の飛行の状況や翌日のスケジュールが作成されるため、必ず一日に一度は入らなくちゃならないんだけどね。ここでは今日もいろいろなドラマが・・・
たくさんありすぎて書けません。
- 事業用
- 航空機の免許の一種。これの下は「自家用」上は「上級事業用」は廃止されて「定期航空運送事業」。航空学生は固定翼の学生は計器飛行課程の修業前、回転翼は回転翼基礎課程でこの免許を受けて、合格すれば取得できます。
海上自衛隊は指定養成施設になっていて、航空局の試験管の試験を直接受けなくても免許がもらえる。言ってみれば公認の自動車学校みたいなものですね。
事業用操縦士の技能証明を持っていると、操縦で食っていけます。ただしそういう仕事があればの話ですが。自家用では仕事は(ほとんど)出来ません。
- しずみ
- 飛行機が沈んでいく事。じゃない。着陸における最終段階、滑走路上の接地点付近において、(呼び起こしの後)少しずつ降下していくことを称して沈みと言う。
学生によってはこれがなかなか感じ取る事ができず、結果としてソロに出れないという事もあるぐらい大事な事。「今日はじめて沈みがわかった」などという。
- 姿勢(しせい)(講演・講義などの)概要,摘要,要旨;教授細目,時間割
- 一般には体の状態をいう(あいつは姿勢が良いとか)。飛行教育においては飛行機の姿勢を言う。つまり機首位置(ピッチ)とかバンクの状態をあわせている。英語ではAttitude.
これがわかっていないと飛行機を操縦することは出来ない。車の場合、針路だけ(つまりヨーイング)を見ていれば重力とタイヤの共同作業で残りの要素(ピッチングとローリング)を決めてくれるが
飛行機の場合それらすべてを人間(あるいは機械)がコントロールしなければならないため、少なくとも車の場合よりは外の景色を見ていなければならない。これが姿勢を保つと言う事である。すなわち操縦すると言う事。
操縦とは姿勢のコントロールのことなのだ。
- 視程
- 見とおしのしやすさ。航空機における気象条件の要素は、雲の高さ(シーリング)と視程に分けられます。飛行場ごとに定められている最低進入気象条件もこの二つで定義されています。
たとえば、管制圏におけるVMCとIMCの境目は「5キロ」の「1000」。つまり、視程(この場合は地上視程の卓越視程)が5キロメートル以上、シーリング1000フィート以上であればVMCとなります。
パイロットにとって重要なのは地上視程もさる事ながら、飛行視程です。でもこれは本人にしかわからないこと。ここからいろんなウラ話が・・・(以下内緒)
- じゅんけん(巡検)
- 見まわって取り調べること。その昔、鎌倉時代に役人が各地を見まわって人々の生活状態や農産物の作柄を見まわっていたそうな。
海軍においては、毎日2000(夜8時のことをこう言います)に当直士官が居住区を見まわって隊員の健康状況や施設の整備状況を見まわること。海上自衛隊は、
この伝統を受け継ぎ、毎日実施している。なんとなく物悲しいラッパの音に乗って、今日も行われている(はず)
学生時代は、この巡検が恐怖だった。甲板掃除の出来が悪いと、よにも恐ろしい罰直が・・もう書けない。
- シラバス(英:SYLLABUS)
- (講演・講義などの)概要,摘要,要旨;教授細目,時間割。飛行教育の基本。各ステージを細分化し、それぞれのホップの事をこう呼びます。または、そのホップに対応した表定評のことを指すときもあります。
- スケジュール(英:SCHEDULE)
- あらかじめ決められた予定、計画のこと。日程表。自衛隊では日命(日日作業命令)ともいう。要するに翌日の予定。どの学生がどの教官と飛ぶのかと言うこと。教官は、どの学生と当たってもほとんど気にしないが、
どうも学生はそうじゃないらしい。スケジュールによってその夜の寝心地がだいぶ違うということである。
- ソロ(英:SOLO)
- 一般には一人で行うこと。航空業界でも一人で操縦すること。ただし普通はイニシャルソロのことを指して、「あいつ、もうソロに出たのか」「そうらしい、オレよりへたくそだったのに」(誰が決めたんだよ。ええー)
という様に使用される。でも、海上自衛隊では学生は一人で飛ぶことはありません。右席にはちゃんと同期の学生が乗ってチェックリストの読み上げとか、見張りの要務を行います。つまり互乗飛行。でも呼び方は「ソロ」(関連:デュアルソロ)
先頭へ戻る
た行
- たい(日:隊)
- 一般に自衛隊のことを省略してこう言います。「ちょっとタイまで行ってくる。」「それはタイにおいてあるから・・」
という感じ。ちょっと前のこと、うちの家族のこういう会話を聞いた近所の奥さんが、「すごいわねえ、そんなにしょっちゅう海外旅行してるの」と誤解されたことがありました。
そうです。「Thailand」(東南アジアのタイ国)と間違えられたのですね。
- たいしゃ(日:隊舎)
- 自衛隊の中にある隊員の居住区のこと。島根県の出雲大社ではありません。居住区とかデッキ(英:DECK)と呼ばれることもあります。(候補生デッキとか)
ここでいうデッキは船の甲板のことです。
- ダウンウインド(英:Down Wind leg)
- 場周経路のうち、(通常は)風を背に受けて飛行する部分。ついでに知らない人のために、ここで説明をしておくと、飛行機は通常は風に向かって離陸や着陸を行います。なぜなら、飛行機は地面に対して運動すると言うよりも
空気に対して運動しているので、向かい風で飛行すれば地面に対しての速度がゼロであっても、風速の分だけ前進速度を得ているのと同じだからです。もし、追い風で離着陸をするとその滑走距離は風速にもよりますが10ノット程度でも約1.5倍程度に伸びるようです。
当然の事ながら必要とする滑走路は短いほうが良いので、風に対して離着陸する事になるのです。そのため、着陸コースに進入するときは風を背にして飛ぶ部分が出てきます。詳しくはここを見てください。
- 戦う翼、ジェット戦闘機
- ご存知、当サイトの親分です。先日公認の証として、タイトルロゴをいただき、こうして堂々と営業活動をしております。早く追いつきたく日々努力しておりますので今後もよろしくお願いいたします。
- タッチアンドゴー(英:Touch And Go)
- TGLとも書く事がある。連続離着陸訓練の事。早口で言うと「たっちゃんGO」。達也君元気でやっているかな?
- たま(玉)
- 飛行機には「針」と「玉」があります。略して「はりたま」これだけじゃ何の事かわからないでしょう。「針」と言うのは旋回計の事。とっても幅の広い針で、ひと針幅もふれると、その旋回率は「標準旋回」と呼ばれるレートになります。つまり、一秒当たり3度、10秒で30度の旋回。Standard Rate Turnともいいます。
あ、針じゃなくて、玉の話ですね。玉は「傾斜計」いってみれば大工さんなんかが使っている水平をだす道具のようなもので、曲がったガラス管の中にアルコールと玉が入っているだけの簡単なものです。飛行機が飛行中、その姿勢と進行方向が一致していれば、重心は真下にかかるため玉は中央にありますが、釣り合いが取れていない状態(ラダーを踏んでいたり、
トリムがきちんと取れてなかったりした場合は、球が中央から外れた状態になります。(これは旋回中も同じ)そんな時、教官は「玉が飛んでいるぞ」と注意するのです。(もっと簡単に「玉、玉」とだけ言う人もいます。)T−5は初級練習機なので、一般の感覚からみると、きわめて巨大な針と玉を備えています。
- たんか(日:短靴)
- 某姉妹サイトで募集していた「短歌」ではありません。短い靴のこと。たんぐつ。これだけでは想像できないでしょうが、何のことはない、普通の革靴のことです。
ビジネスシューズみたいな。海上自衛隊では、幹部になると夏服の時は真っ白な短靴を履くようになります。海曹士は夏でも冬とおなじ黒靴です。
でもこの白い靴は手入れが大変なんだなあ。すぐ薄汚れちゃって。
- 単独飛行
- 操縦士が航空機の単独の占有者である間の飛行とICAOの定義にある。ということは、一人で飛ぶ事ではないのだ。だから201のソロは学生互乗で飛ぶ。右席の学生は操縦に関しては一切口出ししてはならないのだよ。
- 手が痛い(てがいたい)
- フライトを終えて教官室に帰ってきた教官がよく言う言葉。飛行作業なのになぜてがいたくなるのでしょう。特に、左手が痛くなるようです。世界七不思議のひとつ。
同様の言葉に「腰が痛い」や「お尻が痛い」があります。
- デュアルソロ(英:DUAL SOLO)
- デュアルは2個の、あるいは二人のこと。ソロは一人のこと。じゃあこの言葉はいったいなんじゃ。(だから用語集を作ったんだろ)
飛行のシラバス上、ソロフライトをするホップが時々あるんですが、天気が悪かったりして、学生だけではどうしても飛ぶことができず、
かといってスケジュール上、もう引き伸ばすことができないと言う極限状態になった時これが発動される。つまり本当は学生だけで飛ぶところを
教官と同乗して、ソロのシラバスを消化すること。この場合、教官は「想定」学生であるため、身の危険(そんな大げさな)を感じた時意外は
一切口を出さない。でも学生にとっては、ホントのソロか、デュアルソロかでえらい違いだよなあと思っているはず。ちなみに教官と飛ぶことを「同乗飛行」
ソロで飛ぶすなわち学生二人で飛ぶことを「互乗飛行」と呼んでいます。
先頭へ戻る
な行
- 夏服(日:なつふく)
- 夏に着る服。summer clothes。海上自衛隊の制服にはいろいろな種類があるんですが、大きく別けると夏服と冬服になります。
同じ夏服でも、第1種、第2種、第3種とわかれています。第1種が通常「礼装」と呼ばれるもので詰襟の長袖。第2種が略衣と呼ばれる
半そでのもの。第3種がワイシャツにポケットと階級章を着けたような民間パイロットみたいなもの。写真はそのうちに・・
でもって、TPOに合わせて使い分けていますが一般的には半そでのものを多用しています。冬服から夏服にあるいはその逆に切り替わる日は
大体決まっていますが、その前後2週間ぐらいは「混用期間」といってどちらを着ても良いようになってます。だからこの期間の隊内は、まるで制服の見本市のような様相を示します。
- にーぱっと(英:nee pad)
- またの名をクリップボード。飛行中にメモを取ったり資料を見たりするときに便利なのがこれ。ひざのちょっと上のところにゴムバンドで括り付けて、メモ用紙なんかをはさんだりします。
学生によっては、ここに山のような資料を挟んできますが、キャノピーを明けた状態ではすごい風が吹き込んだりするのでよく飛ばされて、泣く思いをしているようです。
だいたい、持って行っても見る暇なんて無いし、見てたら何か言われるよ。「どこ見てんじゃー」てね。手順ぐらいちゃんと覚えてから乗りなさいね。
先頭へ戻る
は行
- 罰直
- こ、これは・・項目を書いたものの内容は恐ろしくてかけません。某三大新聞のひとつに糾弾される恐れあり。自主的体力練成運動とでも申しましょうか・・^_^;
- ピーエックス(PX)
- Post Exchangeのこと。隊内にある売店です。直営と委託の2種類あって、タオルや洗面器、石鹸からお菓子、みやげ物(萩焼きも)雑誌、文房具から、テレビまでたいていのモノは売っているところ。
夕方になると学生さんは大挙して出かけて、大量の菓子を買ってくるらしい。
- 飛行時間
- 飛行機に乗っている時間の事。ただし、民間の旅客機に乗っているような時間は含まれない。自衛隊における飛行時間は、離陸のために滑走を開始した時間から、着陸し、エプロンに帰投してエンジンを停止した時間までと決められている。(民間とは違いますね)
だから、乗りこんで、エンジンをかけてタクシーしても、離陸するまではその時間はカウントされないのだ。そのかわり着陸後にもたもたと地上滑走して時間を稼げばそれだけ飛行時間は伸びると言うわけ。でも実際は着陸したら早く飛行機から降りたいから
そんな事するものはいません。ちなみに飛行時間が3000、6000、9000、と伸びるにつれて、その人の飛行経歴にはくがつきます。つまり防衛記念章を付けられるようになると言う事。
私はようやく先日6000時間に到達しました。まだまだこれから。
- 罷免
- 職務をやめさせること。免職。すなわち学生の身分で無くなる事。世の中にはいろんな人間がいてそれぞれ個性を持っている。当然、ある職務に対して向き不向きがあり、たまたまそのひとは飛行学生に向いていなかったと言う事です。
ここで大事なのは「パイロット」に向いていないのではなく「飛行学生」に向いていないと言う事です。詳しくはFAQを見てください。
- ピンク(英:PINK)
- 桃色のこと。学生を罷免へと導く恐怖の色。どういうことかって?。つまり、その日のフライトの出来が悪くて、定められた技量に達していないと判断された時、
そのホップは不合格と判断され、「不合格記録表」というものを渡される。この紙がピンク色をしているためこう呼ばれる。
- ヘルメット
- みんな知っているあれです。頭を保護する奴。次の課程である徳島ももうすぐこれを使わずにヘッドセットを使うようになるらしい。となると海上自衛隊の固定翼機で、ヘルメットをかぶるのはT−5だけになりそうです。
もちろん、頭を保護する道具なんだけど、日常的には、いったい何から頭を保護するのだろうか。
- ホップ(英:HOP)
- 飛行機など速い乗物で)短い旅行をする。とここから来たのかなあ。要するに一回のフライトの事。「今日は午前午後で3ホップも飛んだ、きつかった」という様に使う。
先頭へ戻る
ま行
- 身の危険(日:みのきけん)
- 自分の命が危ないと感じること。もちろん学生、教官とも感じることがあるが、そのシチュエーションはだいぶ異なる。
教官が感じるのは、1.学生が危険操作をした、あるいはしようとした時。2.訓練中急激に天候が悪化して、帰れなくなるかもしれないとき。
3.航空機の異常を感じた時。
学生が感じるのは、1.1項目は教官と同じ。ただし、学生はその行動の直接の結果に対してではなく、それに対する教官の反応に対して身の危険を感じる。
2.天候が悪くて基地に帰れないと、この教官と一緒に一晩よその基地で付合うのかと思うことの恐怖。3.教官の機嫌が急に悪くなった時。あるいは1ホップ目の学生がむちゃくちゃ怒られて降りてきた時。
同じ飛行機に乗っていてもこれだけ感じ方が違うと言うこと。
先頭へ戻る
や行
- やさしい言葉
- その名のとおりなのだが、教官が学生に対してこれを使い始めると危ない。なぜかって?厳しい言葉で教えてるうちは、「こいつを何とかしてパイロットにしてやろう」と思っているのですが、「こいつはもう無理だな」
と思うと、かわいそうなのでやさしい言葉になるのです。これってホント?
- やり直し
- もう一度行うこと。特に有名なのが「着陸やり直し」つまりGO AROUND。着陸復行、WAVE OFFとも呼ばれる。
名古屋空港のA−300の中華航空機事故でちょっと有名になったGo-Aroundだけど、あれは別に危険なものではない。ソロ検定においても
必ず一度は着陸復行をさせて、安全に出来るかどうかを確認する。たとえどんなに着陸がうまくとも、これが出来ない限りはソロに出せないのだ。
大事なことは姿勢がいかに安定しているかと言うこと。もちろんパワーを出すのを忘れるようじゃお話にならないのは言うまでもないか。
先頭へ戻る
ら行
- ラダーの飛行機
- 何を隠そう、このサイトの産みの親。もともとこのページは半分冗談で産まれたものですが、らだーと名乗る方のご指導ご鞭撻により、ここまでやってくる事が出来ました。
このHPの作者は最近寝不足気味ですが、何とかガンバッていられるのもこのお方のお陰と感謝しております。これを読んだ方は感謝の意味を込めてここ
を見に行きましょう。
- ライン
- 列線のこと。列線とは飛行機をきちんと整列させてならべることからこう呼ばれる(と思う)。たぶん
旧海軍時代からの用語。ここで簡単な整備作業を行う部隊を「列線整備隊」という。これは、航空隊の中に所属する部隊で
給油、航空機の誘導、日日点検や飛行前点検、比較的簡単な整備等を行う。これらを総称して「ライン作業」という。
ここは、エンジンをかけた飛行機やランプイン、ランプアウトの飛行機、燃料給油車などが錯綜し、ボーとしていると非常にに危険。
よって、服装から歩き方まで細かいきまりがあり、これが身につくまで徹底的にしつけられる。
- ルーキー(rookie)
- プロ野球の新人選手、新米、初心者、新兵。転じて、わが201教空のコールサイン。以前のKM−2の時は「イエロー(yellow)」だった。
これは単に飛行機の色から来たものだったが、英語の俗語から言うとあまり良い意味は無い。まあ、練習機だから海外に行く事は無いものの、ガイジンサンが聞いたら
とんでもないコールサインだったんじゃないだろうか。ルーキーになってから、各地の管制機関から「Say Type of Aircraft」と良く聞かれる。まだぜんぜん有名じゃない。
先頭へ戻る
わ、を、及び ん
- 腕力(hiroさんアリガト)
- 腕の力。航空学生は体力で勝負。最初のフライトにおいて、水平飛行中エレベータートリムを目いっぱいとって(UP,DOWNとも)
腕の力で支えられないようじゃ駄目ですな。と言うわけではなのだろうけど、おとなりの月教空の学生は食事の前に鉄棒で懸垂をしています。
うちの学生がやってるのは見た事無いけどやってるのかな。あ、替わりによく腕立て伏せしてるからいいのか(^。^)
教官の「腕力」が強すぎると学生がかわいそうとの声もある?
- を、ん
- やっぱりないみたい。